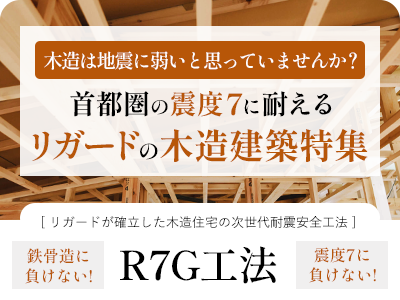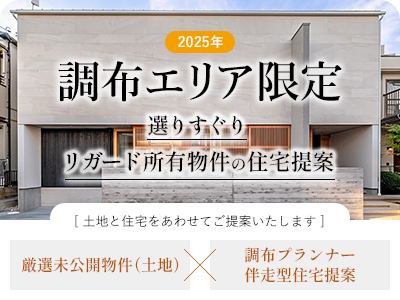Archive
耐震等級3の評価方法基準は二つ 構造計算する場合の費用の内訳は?

注文住宅の耐震性はどうやって計る?
住宅性能表示制度において、耐震性を評価する項目が「耐震等級」です。耐震等級は1〜3の基準がありますが、その内容は以下の通りです。
| 耐震等級1 | 極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震力に対し倒壊せず、希に(数十年に一度程度)発生する地震力に対し損傷しない |
|---|---|
| 耐震等級2 | 等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して損傷を生じない |
| 耐震等級3 | 等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して損傷を生じない |
地震対策というと、耐震の他に「制振」「免震」という言葉も聞いたことがある方が多いと思います。
「耐震」は字の通り「地震に耐える」と言うことなので、建物を固く頑丈にすることで地震による倒壊や損傷を防ぎます。
「制振(制震)」は地震力と逆方向の力を加える部品(ダンパー)を入れ、建物の中は揺れを感じにくくする建物の揺れを制する方法です。
「免震」は免震装置(アイソレータ、ダンパー)を設置し、そこで揺れを吸収し建物自体に揺れを伝えない方法です。
「耐震等級3」なら信頼性は同じ?
耐震等級3の基準が、「等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して損傷を生じない」という、すこし曖昧な文章で書かれていることにお気づきだったでしょうか。
「損傷を生じない」ことをどのようにして確認するのだろう? と疑問を持たれた方は、ぜひその答えに明快に答えられる施工者を選んでくださいね。
以下の文章を読んでおけば、「耐震等級3施工実績あり」という謳い文句には2つの水準があることを理解できます。
耐震等級3取得のための二つの評価方法基準
「限界耐力計算」「保有水平耐力計算」による方法
限界耐力計算と保有水平耐力計算は、「構造計算」と呼ばれるものの一種です。
法律で定められる構造計算の4つの方法については、以下の記事をご覧ください。
それぞれの計算上の(極めてざっくりとした)特徴は、以下のようにまとめられます。
| 限界耐力計算 | 想定される地震力(数百年に1度)を加えた時、各部材が耐えられる力の大きさ(許容応力度)を超えてしまわないか計算する |
|---|---|
| 保有水平耐力計算 | 建物が倒壊するほどの力がどれくらいかを計算する |
現在は、「保有水平耐力計算」の方が精密な計算方法とされています。
ただし、いずれの方法でも、部材レベルでの負荷を計算した上で安全性を評価できるため、「構造計算=品質の高い耐震性の保証ができる方法」と考えて頂くことができます。
リガードでは上記の方法を採用し、耐震性を確保しています。
「階数が2以下の木造の建築物における基準」を満たす方法
これは所謂「4号建築の特例」が使える場合の代替的な方法です。
4号建築については以下の記事をご覧ください。
この方法で計算するのは、以下の項目です。
- 壁量の確保
- 耐力壁線間の距離
- 床組等の強さ
- 接合部の強さ
- 小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔
- 構造強度
これらの項目で基準を満たせば耐震等級3を取得することができます。なぜこの方法で建物の強さが計れるのかと言うと、それは「壁量計算」の発想の延長上にあります。
「耐震等級3」相当の設計に必要な費用って?
耐震等級3の取得にかかる費用は以下の通りです。
- 構造計算費用
- 耐震等級基準を満たすための施工費用
- 申請費用(正式に申請する場合)
正式に耐震等級3を取得するとなると以上の合算の費用がかかり、耐震設計をしない場合に比べて割高になります。
また、「耐震等級3相当の施工を行い、構造計算も行うが、費用と手間がかかるので正式な申請はしない」ケースもあります。真に地震に強い家が建てばそれでよいと考えるならば、視野に入れてみてください。
構造計算された地震に強い家を建てるなら
リガードでは、巨大地震を見据えた耐震性能を目指しており、過去20年全半壊ゼロの実績を誇るSW工法を採用しております。
耐震性を高めるSWパネルを採用することにより、家が丸ごと制振装置となり、安心できる耐震木造住宅を提供しております。数字で確認できる耐震性を求める方は、ぜひリガードまでご相談ください。